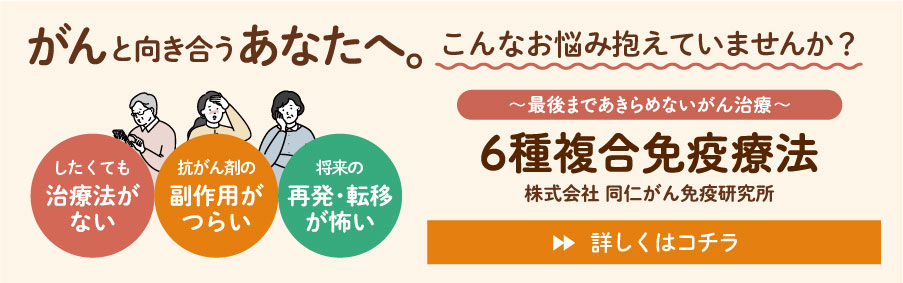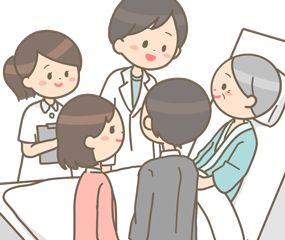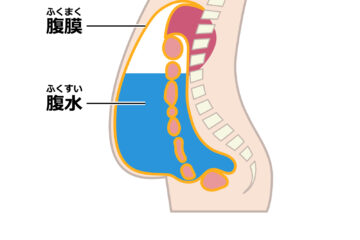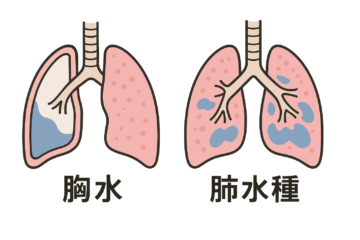がん免疫療法コラム
膵臓がんの原因とは? 危険因子や最新治療法についても詳しく解説
膵臓がんは、胃の裏側にある膵臓に発生する悪性腫瘍です。
膵臓は、消化酵素やホルモン(インスリン、グルカゴンなど)を分泌する重要な臓器です。ここにがんが発生すると、様々な体の機能に影響を及ぼします。
膵臓がんは、早期発見が非常に難しく、進行が速く予後不良ながんとして知られています。
自覚症状が現れた時にはがんが進行しており、治療が困難になることも少なくありません。
早期発見が難しいからこそ、日頃から発生の原因である危険因子について理解を深めておくことが重要です。
今回の記事では、膵臓がんの原因や最新の治療法について詳しくご紹介します。
【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。
INDEX
膵臓がんの原因と危険因子(リスクファクター)

膵臓がんの発症の原因としては、いくつかの危険因子が関与していることが分かっています。
特に、生活習慣や遺伝的要因が発症リスクを高めると考えられています。
遺伝的要因
膵臓がんの発症には、遺伝的要因が関与することがあります。特に近親者に膵臓がんを発症した人がいる場合は発症リスクが高まると考えられています。
家族性膵がん
家族性膵がんとは、両親や兄弟などの近親者に膵臓がんを発症した人が複数いる場合、同じ家系で発生する膵臓がんを指します。一般的に親族で2人以上の膵臓がん患者さまがいる場合は発症リスクが通常より高まるとされています。
BRCA2、PALB2、CDKN2Aなどの遺伝子変異が関与していると考えられています。
特に、BRCA2遺伝子変異を持つ人は、それが乳がんや卵巣がんの原因となり、発症リスクも高くなるため注意が必要です。
遺伝性膵炎
遺伝性膵炎とは、遺伝的な要因によって発症する慢性膵炎です。幼少期から膵臓の炎症が繰り返し起こるのが特徴です。膵炎を長期間患うと、膵臓の組織が傷つき、膵臓がんの発症リスクが高まることが知られています。
遺伝性膵炎は幼少期から思春期にかけて発症することが多く、PRSS1、SPINK1などの遺伝子変異が関与しています。繰り返す腹痛悪心 、嘔吐、下痢などの症状が現れ、長期的な膵炎による糖尿病や膵臓がんの発症リスク上昇も懸念されます。
合併疾患
膵臓がんは、いくつかの疾患と関連があり、その疾患が原因となり発症リスクを高めることが分かっています。特に、膵臓の機能に影響を与える疾患や代謝に関わる疾患が関係することが多いです。
糖尿病
糖尿病は膵臓がんと深い関係があり、糖尿病患者さまは膵臓がんのリスクが約2倍に上昇することが知られています。また、膵臓がんによりインスリンの分泌量が低下し、糖尿病が悪化する可能性があります。
慢性膵炎
慢性膵炎は膵臓の炎症が長期間続く疾患です。長期間の炎症により膵臓の細胞が損傷を受けることで、膵臓の機能が徐々に低下していき、膵臓がんの発症リスクが約10倍に高まると考えられています。特にアルコール性慢性膵炎や遺伝性膵炎の患者さまは、膵臓がんのリスクが高いとされています。
膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)・膵嚢胞
膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)や膵嚢胞は、膵臓内でできる液体がたまった袋状の病変で、一部は膵臓がんへ進行する可能性があります。特にIPMNは、膵管に沿って発生し、粘液を分泌する腫瘍であり、がん化リスクが高いタイプも存在します。
特に、一定以上の大きさになったり、膵管に影響を与えたりする場合は、外科的切除が検討されます。
生活習慣
膵臓がんの発症には、生活習慣も大きく関与します。特に、食事や運動、喫煙や飲酒などの習慣が膵臓の健康に影響を与え、がんのリスクを高めることが知られています。
喫煙
喫煙は膵臓がんの大きな危険因子の一つであり、喫煙者は非喫煙者に比べて発症リスクが約2倍になると報告されています。タバコの煙に含まれる有害物質が膵臓の細胞にダメージを与え、がん化を促進すると考えられています。
特に、長年喫煙している人や1日の喫煙本数が多い人は発症リスクが高まります。
飲酒
過度の飲酒も膵臓がんのリスクを高めるとされています。アルコールの摂取が慢性膵炎の原因となり、長期間の炎症が膵臓の細胞にダメージを与えることで、がんを発症する可能性があります。
特に、アルコール依存症の人や長期間大量の飲酒を続けている人は注意が必要です。
食生活
高カロリー・高脂肪の食事や加工食品の摂取は、膵臓がんのリスクを高める可能性があります。特に、糖分や飽和脂肪酸の多い食品は肥満を引き起こし、膵臓の負担を増やす原因になります。
野菜や果物を積極的に摂取し、脂肪の多い肉、加工肉、揚げ物など、脂肪の多い食品の摂取量を抑えることで膵臓がんのリスクを軽減することができます。
肥満
肥満は膵臓がんのリスクを高める要因の一つとされており、特に内臓脂肪の多い内臓肥満は、膵臓の慢性的な炎症を引き起こし、がんの発生につながる可能性があります。肥満者の発症リスクは非肥満者に比べて約1.5倍です。
特に内臓脂肪の多い内臓肥満は…がんの発生につながる可能性があり、発症リスクは非肥満者に比べて約1.5倍です
また、肥満に伴うインスリン抵抗性の増加が、膵臓の細胞に悪影響を及ぼすとも考えられています。
運動不足
運動不足は肥満を引き起こすだけでなく、糖尿病や慢性炎症のリスクを高めることで膵臓がん発症の原因となる可能性があります。膵臓の慢性炎症は、DNAの損傷や活性酸素の増加、サイトカインの影響などによりがんのリスクを高めます。
週に150分以上の有酸素運動が推奨されており、ウォーキングや軽いジョギングなど、日常的に体を動かすことが発症リスクの軽減につながります。
膵臓がんのその他の危険因子
膵臓がんの発症には、遺伝的要因や生活習慣のほかに、さまざまな環境要因も関与しています。
近年の研究では、血液型や特定の感染症、職業的な化学物質への曝露(何かの物質や、外の空気や光などに直接さらされること)などが、膵臓がんのリスクを高める可能性が指摘されています。
ピロリ菌・B型肝炎ウイルス
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)やB型肝炎ウイルス(HBV)の感染は、それぞれ胃や肝臓に慢性的な炎症を引き起こし、胃がんや肝細胞がんのリスクを高めることで知られています。近年では、これらの感染症が全身の炎症を悪化させ、膵臓にも負担をかけることで、膵臓がんのリスクを高める可能性が指摘されています。
ピロリ菌感染がある場合は除菌治療が推奨され、B型肝炎ウイルス感染の予防にはワクチン接種が有効です。すでに感染している場合は、定期的な検査を受け、肝臓だけでなく膵臓の健康状態にも注意を払うことが重要です。
膵臓がん発見後の最新治療
膵臓がんは早期発見が難しく、進行した段階で診断されることが多いという特徴があります。しかし、近年の医療の進歩により、新たな治療法が開発され、患者さまの生存率や生活の質の向上が期待されています。
膵臓がんの最新治療には以下のようなものがあります。
| 治療法 | 特徴 |
| ロボット支援手術 | 低侵襲で精密な手術が可能 |
| 免疫チェックポイント阻害剤 | 免疫の働きを活性化し、がん細胞を攻撃 |
| 分子標的薬 | がん細胞の特定の分子を標的とする治療 |
| がんワクチン療法 | 免疫系を利用してがん細胞を攻撃 |
| 放射線併用療法 | 化学療法と組み合わせて局所制御を強化 |
これらの治療は従来の手術や化学療法と組み合わせて用いられることが多く、個々の患者さまの状態に応じて最適な治療法が選択されます。
特に、免疫療法や分子標的薬の進歩により、これまで治療が難しかった進行膵臓がんに対しても新たな希望が広がっています。
膵臓がんの新しい治療法:免疫療法

膵臓がんは初期段階ではほとんど自覚症状が現れないため、発見された時には病状が進行しているケースが少なくありません。
特にステージ3、ステージ4と診断された場合、がんが既に他の臓器に転移しているため、従来の治療法では根治が難しい場合もあります。
しかし、近年では、がんの進行を抑え、生活の質(QOL)を維持するだけでなく、根治も目指せる新しい治療法として、免疫療法が注目されています。
免疫療法は、私たちの体の中に存在する免疫細胞の力を利用して、がん細胞を攻撃する治療法です。近年、研究開発が急速に進み、より高い治療効果が期待されています。
その中でも、特に注目されているのが6種複合免疫療法です。
これは、患者さま自身の免疫細胞を体外に取り出し、培養して活性化・増殖させた後、再び体内に戻すことで、がん細胞に対する攻撃力を強化する治療法です。
以下では、この6種複合免疫療法について、そのメカニズムや効果、治療の流れなどを詳しく解説していきます。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00