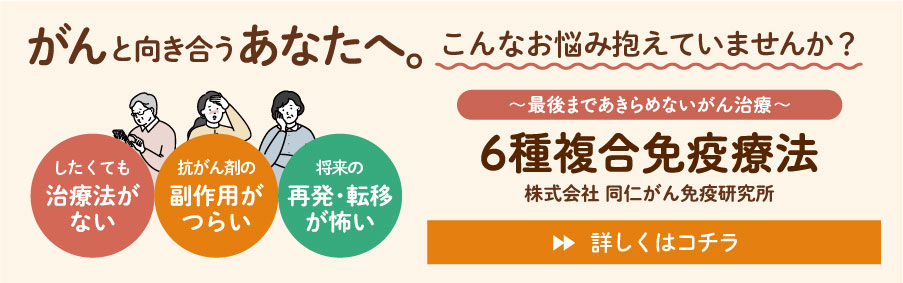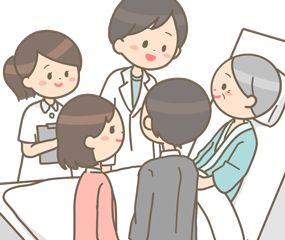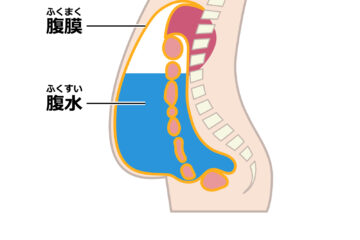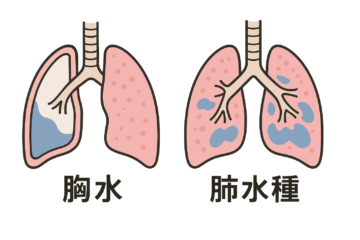がん免疫療法コラム
胃がんと吐血の関係とは? 検査や治療法についても解説
胃がんが進行することで現れる症状の一つが「吐血」です。
胃の内部でがん細胞が増殖し、腫瘍が胃壁を侵食すると、出血が引き起こされ、それが吐血として表れます。
吐血はその出血量や状態によって、非常に危険なサインとなる場合があります。
特に胃がんによる吐血はがんの進行を示す重要な指標となり、迅速な対応が求められます。
今回の記事では、胃がんによる吐血の原因、症状、治療法について詳しく解説し、吐血が示す他の疾患についても解説します。
【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。
INDEX
胃がんと吐血の関係とは
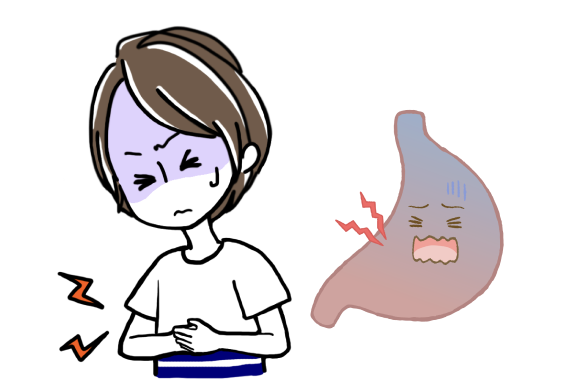
吐血は、胃がんが進行した際に見られる症状の一つです。
胃がんが成長すると、胃の内壁が傷ついたり、腫瘍が潰瘍化したりすることで出血が起こり、それが吐血として現れます。
胃がんによる吐血は、鮮やかな赤色または暗赤色で、出血量が多い場合にはショック状態に陥ることもあります。
胃がんによる吐血が起こる主な原因は、以下の通りです。
- 腫瘍の潰瘍化:がん細胞の胃粘膜侵食による潰瘍形成
- 血管の破壊:腫瘍の増大による胃壁の血管の破壊
- 腫瘍表面の脆弱化:がんの炎症進行による腫瘍表面の脆弱化
吐血が見られた場合以上が原因の可能性もありますが、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を原因として起こる可能性もあるため、自己判断せず医療機関を受診することが重要です。
吐血をした場合の対応と治療
吐血は緊急性の高い症状であり、発生した場合は速やかな対応が必要です。
吐血が起こった際の適切な対応と治療法について解説します。
吐血時の対応
- 安静にする:無理に動かず、上半身を少し起こした状態で安静にする。
- 吐いた血の確認:血液の色や量、混ざっている内容物を確認する。
- 医療機関を受診:大量の吐血やめまい、冷や汗、顔面蒼白がある場合は、すぐに救急車を呼ぶ。
吐血の治療法
吐血の原因が胃がんである場合、以下の治療が検討されます。
- 内視鏡治療:内視鏡を用いて出血部位を止血する。クリップで血管を挟んだり、止血剤を注入したりする。
- 輸血・点滴:出血量が多い場合、輸血や点滴で体の状態を安定させる。
- がん治療:止血後、手術や放射線治療、薬物療法などでがんそのものを治療する。
吐血で考えられる胃がん以外の病気
吐血は胃がんの症状として知られていますが、他にもさまざまな病気が原因で起こることがあります。
食道や胃、十二指腸などの消化管に異常がある場合、血管の損傷や炎症が引き金となり吐血が発生します。
また、肝臓疾患や血液の凝固異常によっても吐血が引き起こされることがあります。
吐血の原因は一つではないため、自己判断せず、速やかに医療機関で正確な診断を受けることが大切です。
胃潰瘍
胃潰瘍は、胃の粘膜が傷つき、ただれる病気です。
主に胃酸と胃粘膜のバランスが崩れることで発症します。ピロリ菌感染や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の服用、ストレスが原因となることが多いです。
胃潰瘍が進行すると、潰瘍部分が胃壁の血管を損傷し、吐血や下血が起こることがあります。
吐血した血液は赤色または黒っぽい色になり、腹痛や胃もたれ、食欲不振を伴います。
治療には胃酸を抑える制酸薬の使用や、原因となるピロリ菌の除菌が行われます。
十二指腸潰瘍
十二指腸潰瘍は、胃とつながる十二指腸の粘膜が傷つきただれる病気です。
主な原因はピロリ菌感染や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の服用で、胃酸の分泌過多やストレスも影響します。
食後ではなく空腹時や夜間に、みぞおち付近の痛みが強くなる症状が特徴です。
潰瘍が進行し、血管が損傷すると、吐血やタール状の黒い便(下血)が見られることがあります。
治療には、胃酸の分泌を抑える制酸薬や胃粘膜保護薬が使用され、ピロリ菌感染が原因の場合は除菌治療が行われます。
食道静脈瘤破裂
食道静脈瘤破裂は、食道の静脈が膨らみ、破裂することで吐血を引き起こす病気です。
主に肝硬変などの慢性肝疾患が原因で、肝臓の血流が滞り、食道の静脈に過度な圧力がかかることで発症します。
破裂すると、大量の鮮血の吐血が起こり、重篤な場合はショック状態に陥ることもあります。
黒い便(下血)、めまい、冷や汗などの症状が特徴です。
治療は内視鏡による止血処置が行われ、破裂予防のために薬物療法やバンド結紮術が用いられます。
マロリーワイス症候群
マロリーワイス症候群は、激しい嘔吐や咳、腹部への強い圧力によって、食道と胃のつなぎ目(噴門部)の粘膜が裂けて出血する病気です。
飲酒後の嘔吐や妊娠中のつわり、暴飲暴食がきっかけで発症することが多いです。
症状として、突然の鮮やかな赤い吐血が特徴で、腹痛や胸の違和感を伴うこともあります。出血量が少なければ自然に止まることもありますが、大量に出血した場合は貧血やショック状態を引き起こす可能性があります。
治療は内視鏡による止血処置が一般的です。症状が軽い場合は、安静と投薬で改善することもあります。
胃がんの検査
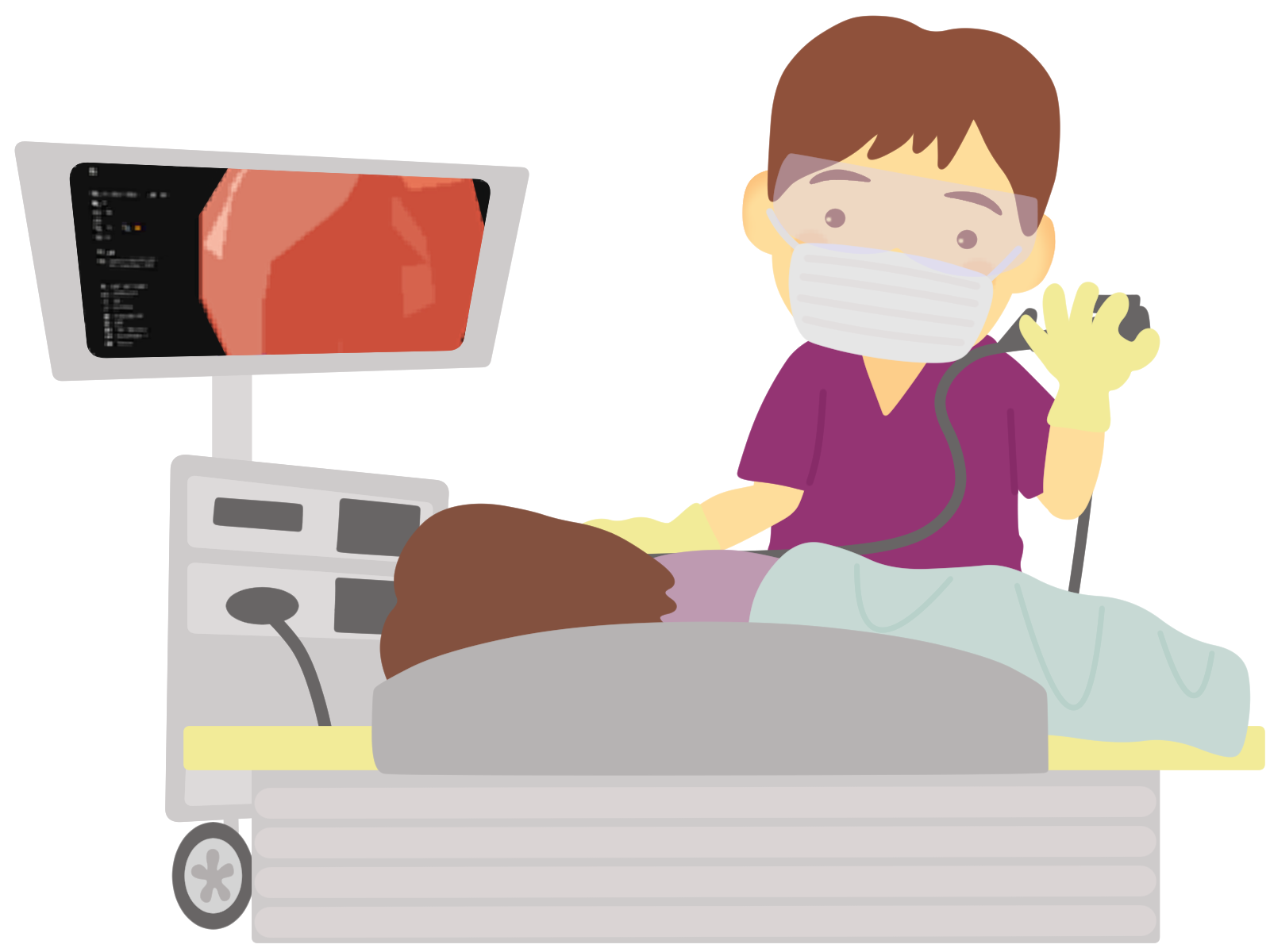
胃がんの検査にはいくつか種類があり、症状やリスクに応じて医師が選択します。
胃内視鏡検査(胃カメラ)
胃内視鏡検査は、最も一般的で精度の高い検査です。口または鼻から内視鏡を挿入し、胃の内部を直接観察します。異常が見つかった場合、組織の一部を採取し、生検(病理検査)でがん細胞の有無を確認します。早期がんの発見に有効で、ポリープの切除も可能です。
バリウム検査(胃X線検査)
バリウムを飲み、胃の形や動きをX線で撮影する検査です。胃の壁の凹凸や異常な影を調べます。内視鏡検査が苦手な方や、集団検診で広く用いられていますが、早期がんの発見には限界があるため、内視鏡検査が推奨されることが多いです。
腹部超音波検査・CT検査
がんの進行具合や転移の有無を確認するために行う検査です。腹部超音波検査は痛みがなく手軽に受けられますが、詳細な評価にはCT検査が適しています。
スキルス胃がんと吐血
スキルス胃がんは、胃壁にがん細胞が広がり、胃壁全体が硬く厚くなる特徴的な進行がんです。
自覚症状が現れにくく、発見時にはすでに進行していることが多いです。
スキルス胃がんが進行すると、胃壁の血管が破壊されたり、腫瘍が潰瘍化したりして吐血が起こることがあります。
吐血の色は鮮やかな赤色または暗赤色で、大量に出血する場合もあります。
スキルス胃がんは進行が速いため、吐血以外にも体重減少、腹痛、食欲不振といった症状が現れることがあります。
胃がんの治療法
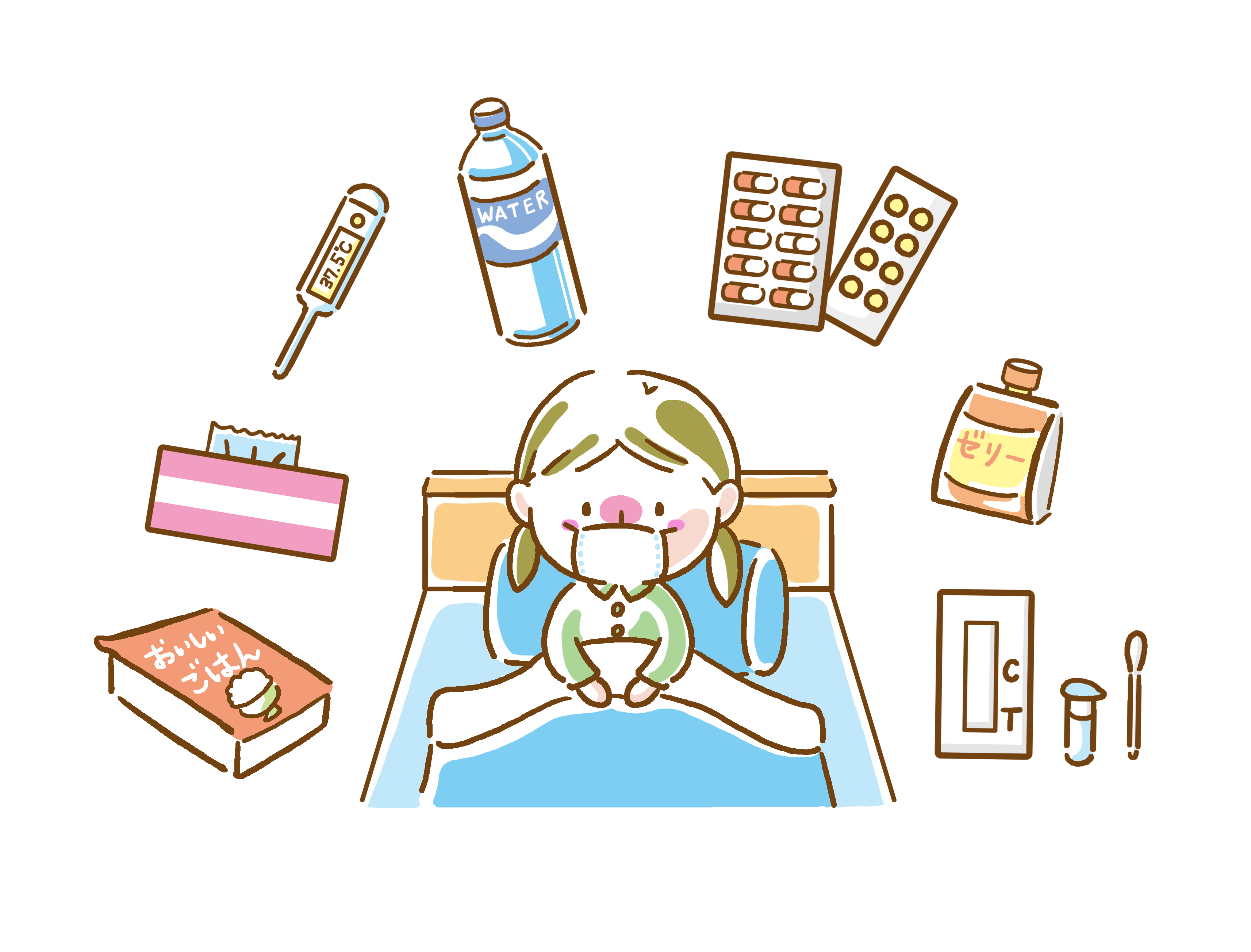
胃がんの治療法は、がんの進行度や患者さまの体調に応じて選択されます。
主な治療法には、がんを切除する手術療法、薬でがん細胞の増殖を抑える化学療法(抗がん剤治療)、放射線を用いてがんを縮小させる放射線治療があります。
早期がんでは内視鏡治療が選択されることもあります。
進行がんの場合は患者さま一人ひとりの状態に合わせ、医師と相談しながら緩和ケアを含め総合的に治療を選択していくことが大切です。
内視鏡治療
内視鏡治療は低侵襲(できるだけ体を傷つけないこと)な治療法で、がんが粘膜内にとどまっている場合やリンパ節転移のリスクが低い場合に適応されます。
主な内視鏡治療は以下の通りです。
- 内視鏡的粘膜切除術(EMR):小さな早期がんを粘膜ごと切除する方法。
- 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD):大きな病変や広範囲のがんを一括で切除する方法。再発リスクが低い。
内視鏡治療では開腹手術が不要で、内視鏡を口から挿入し、胃の内部を観察しながらがんを切除します。
傷が残らないため、体への負担が少なく、手術と比べて回復が早いのが特徴です。
手術
手術はがんが進行している場合や内視鏡治療が適応できない場合に選択され、がんが発生した部位とその周囲の正常な胃、転移の可能性があるリンパ節を一緒に切除します。
主な手術の種類は以下の通りです。
- 胃部分切除術:胃の一部を切除する手術で、早期がんや局所に限られたがんに適している。
- 胃全摘術:胃を全て切除する手術で、進行がんに対して行われる。食道と小腸をつなげる再建手術が必要。
- 腹腔鏡下手術:小さな切開でカメラや器具を挿入し、低侵襲で行う手術。
手術療法はがんを根治できる可能性が高く、症状の改善が期待できます。
注意点として、手術後は食事量が減少し消化吸収に影響が出ることがあります。
また、回復には時間がかかるためリハビリや栄養管理が必要です。
手術の方法はがんの進行度や患者さまの体力によって異なるため、医師としっかり相談しましょう。
薬物療法
薬物療法は手術前後の補助療法や、手術が難しい進行・再発胃がんの治療として用いられます。主に化学療法(抗がん剤治療)、分子標的治療があります。
【化学療法(抗がん剤治療)】
がん細胞の増殖を抑える薬で、がんの縮小や進行抑制を図ります。主な薬剤にはシスプラチンやフッ化ピリミジン系薬剤(5-FU、TS-1)があります。副作用として吐き気、脱毛、免疫力低下が現れることがあります。
【分子標的治療】
がん細胞特有の分子を狙い撃ちし、正常細胞への影響が少ないのが特徴です。代表的な薬にはトラスツズマブ(HER2陽性胃がん向け)があります。
放射線治療
放射線治療は手術が難しい場合やがんの進行抑制、症状の緩和を目的として行われたり、手術後の再発予防や薬物療法と組み合わせて治療効果を高める場合にも用いられます。
高エネルギーのX線や電子線を照射し、がん細胞を破壊する治療法です。
放射線治療の種類
- 外部照射:体の外から放射線を照射してがん細胞を攻撃します。治療は1回15〜30分程度で、数週間にわたって通院が必要。
- 定位放射線治療:高精度の照射でがん組織に集中して放射線を当てる方法。
放射線療法は体への負担が少なく、手術と異なり切開しないため回復が早い治療で、痛みや出血、胃の閉塞などの症状を軽減します。
副作用として、皮膚の炎症や赤み、吐き気、食欲不振、疲労感などが現れることがあります。
胃がんと免疫療法
吐血を伴う胃がんでは、免疫療法も選択肢の一つです。
免疫療法とは、免疫の力を利用する治療法です。
現在行われている免疫療法にはさまざまな種類がありますが、大きく以下の2つに分けられます。
- 免疫チェックポイント阻害薬による治療
- 免疫細胞療法
吐血が伴うステージ3やステージ4の胃がんでは、上記2つの治療法を検討することができます。
免疫チェックポイント阻害薬による治療
進行した胃がんで検討される治療法として、免疫チェックポイント阻害薬があります。
免疫細胞であるT細胞は、がん細胞が出す物質に邪魔をされて攻撃にブレーキがかかっています。
免疫チェックポイント阻害薬はブレーキを解除する薬で、さまざまな種類があり、それぞれ有効ながんの種類が異なります。
現在、胃がんの治療で承認されている免疫チェックポイント阻害薬は、以下の通りです。
- オプジーボ(ニボルマブ)
- キイトルーダ(ペムブロリズマブ)
免疫チェックポイント阻害薬による治療で生じる可能性がある主な副作用は、以下の通りです。
- 間質性肺炎
- 重症筋無力症
- 心筋炎
- 筋炎
- 横紋筋融解症
- 大腸炎
- 重度の下痢
- 1型糖尿病
- 免疫性血小板減少性紫斑病
- 肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎
- 甲状腺機能障害
- 神経障害
- 腎障害
- 副腎障害
- 脳炎
- 重度の皮膚障害
- 静脈血栓塞栓症
- 注入時過敏反応
免疫細胞療法
がん細胞を攻撃する免疫細胞の力を強化するのが、免疫細胞療法です。
この治療法にはさまざまな種類があり、薬物療法と併用されるケースもあります。
その中で、近年、抗がん剤とあわせて患者さまの免疫力を活用する「6種複合免疫療法」が注目されています。
この治療法は、免疫細胞を活性化し、がん細胞に対する自然な防御力を高める複数の免疫細胞を組み合わせたもので副作用もほとんどなく、抗がん剤治療を補完しながら治療効果の向上が期待されています。
6種複合免疫療法について、以下さらに詳しく解説します。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
②副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
また、費用は治療ごとでのお支払いのため、医療費を一度にまとめて支払う必要もありません。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血によって取り出した免疫細胞を培養し、活性化させた後点滴で体内に戻すという治療法です。方法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果を紹介します。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00