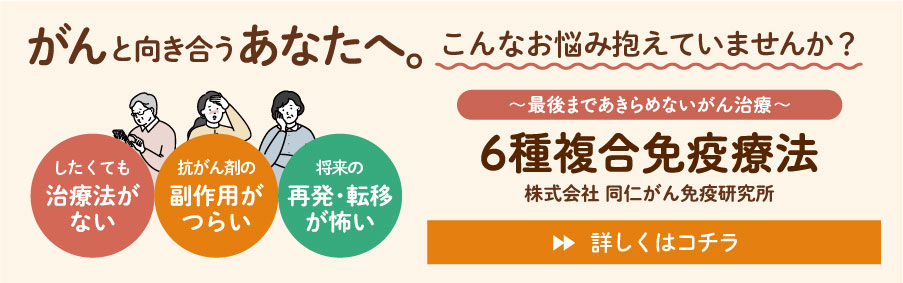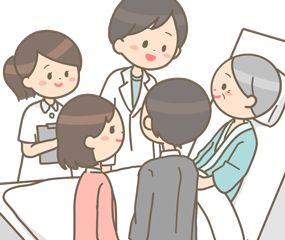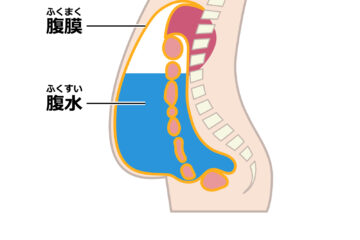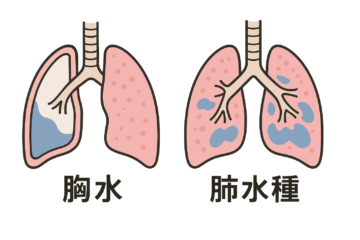がん免疫療法コラム
膵臓がんの検査とは? 画像検査から血液検査まで詳しく解説
膵臓がんは早期発見が難しく、多くの場合進行してから診断されます。
診断には適切な検査が必要です。膵臓がんの検査には、CTやMRI、PET-CTといった画像検査をはじめ、血液検査(腫瘍マーカー)や内視鏡検査、生検など、さまざまな方法が用いられます。
今回の記事では、膵臓がんの検査方法やその特徴について詳しく解説します。
【がんの治療法としておすすめ「6種複合免疫療法」】
副作用が少なく、他の治療と併用できる!
6種複合免疫療法は、患者さま自身の免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻すことで、がんと闘う力を高める免疫療法です。
治療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
6種複合免疫療法をおすすめする理由
- がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
- 副作用が少ないため、体への負担も小さい治療法である
- 入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
がん治療の選択肢の一つとして、6種複合免疫療法もぜひご検討ください。
今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。
INDEX
膵臓がんとは
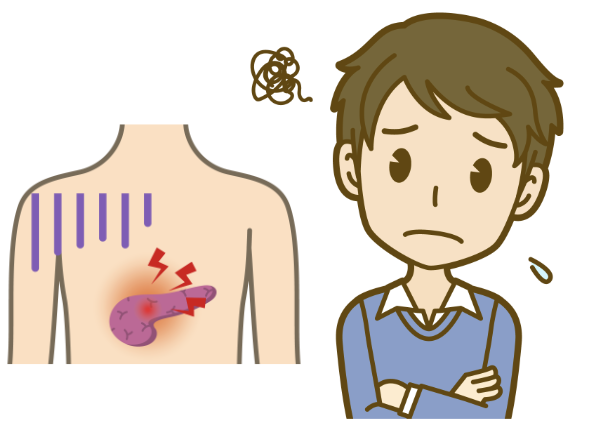
膵臓がんは、膵臓に発生する悪性腫瘍の総称であり、その多くは「膵管がん」と呼ばれる種類に分類されます。
膵臓は胃の後方に位置し、消化酵素を分泌する外分泌腺と、血糖を調整するホルモンを分泌する内分泌腺の役割を持っています。
膵臓がんは、初期段階ではほとんど自覚症状が現れないため、発見時には病状が進行しているケースが少なくありません。
| 特徴 | 内容 |
| 発症年齢 | 高齢者に多く、60~80代での発症が多い |
| 進行の速さ | 早期発見が難しく、進行が速い |
| 主な症状 | 黄疸、体重減少、背中の痛み、食欲不振など |
| 診断の難しさ | 他の病気と症状が似ており、発見が遅れやすい |
膵臓がんの検査:画像診断
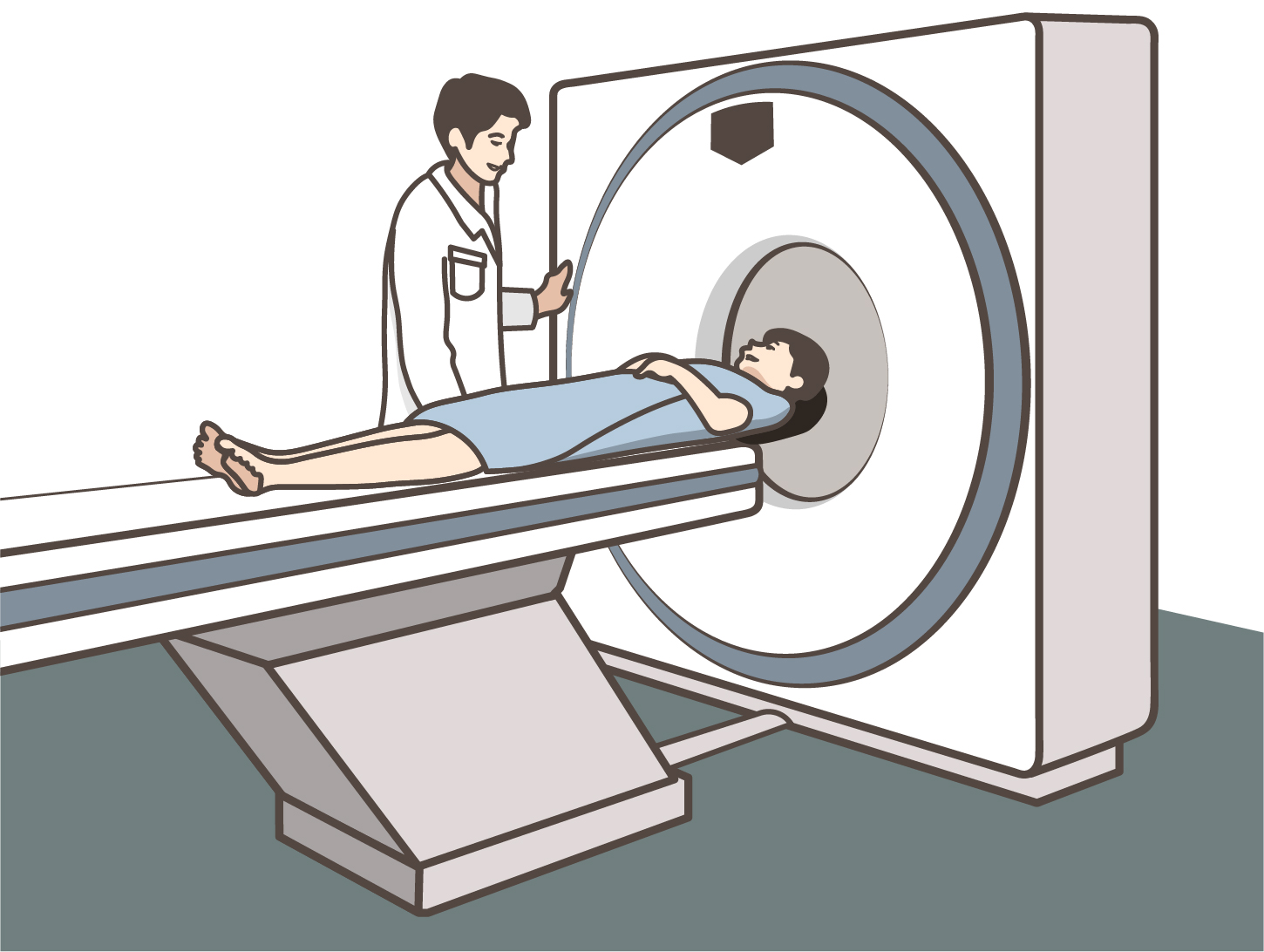
膵臓がんの診断には、さまざまな画像診断技術が用いられます。
膵臓は小さな病変を見つけるのが難しいため、複数の検査を組み合わせて診断の精度を高めます。
画像診断では、膵臓の腫瘍の有無や広がり、血管や周囲の臓器への影響を確認することができます。
腹部超音波検査(エコー)
腹部超音波検査(エコー)は、超音波を使って膵臓の状態を観察する検査です。
体に負担が少なく、放射線を使用しないため、安全性が高いのが特徴です。特に、膵臓の腫瘍や膵管の拡張、周囲の臓器への影響を確認することができます。
ただし、膵臓は胃や腸の奥に位置するため、検査時にガスが影響し、詳細な観察が困難な場合があります。
| 項目 | 内容 |
| 検査方法 | 超音波プローブを腹部に当てて、膵臓の状態を観察する |
| 目的 | 腫瘍の有無、膵管の拡張、膵臓の炎症などを確認 |
| 特徴 | 被ばくせず、痛みなく短時間で実施可能 |
| デメリット | 体型や腸のガスの影響で膵臓全体が見えにくいことがある |
腹部超音波検査は、膵臓がんの初期スクリーニングとして有効ですが、詳細な診断にはCTやMRIなどの追加検査が必要になることが多いです。
CT検査(造影CT含む)
CT検査は、X線を用いて体内を断層撮影し、膵臓の腫瘍や転移の有無を詳しく調べる検査です。
特に造影CTは、造影剤を使用することで血流の違いを強調し、がんの有無や広がりをより明確に判別することができます。
膵臓がんの診断では、腫瘍の大きさや血管・臓器への浸潤を評価するために、造影CTが重要な役割を果たします。
| 項目 | 内容 |
| 検査方法 | X線を用いて膵臓を断層撮影し、立体画像を作成 |
| 目的 | 腫瘍の有無、転移、膵管の拡張や周囲組織への影響を確認 |
| 特徴 | 高精度で膵臓の詳細を観察でき、短時間で検査可能 |
| デメリット | 放射線被ばくがあり、造影剤にアレルギーがある場合は注意が必要 |
CT検査は膵臓がんの診断や進行度の評価において欠かせない検査ですが、より詳細な組織の性質を確認するためにMRI検査が併用されることもあります。
MRI検査
MRI検査は、強力な磁場と電波を利用して体内の詳細な画像を撮影する検査です。
特に膵臓がんの診断では、造影剤を使用する「MRCP(磁気共鳴胆管膵管撮影)」が行われることが多く、膵管や胆管の狭窄・閉塞の有無を確認するのに役立ちます。
CT検査に比べて軟部組織のコントラストが明瞭で、腫瘍の状態や周囲への影響を詳細に評価できるのが特徴です。
| 項目 | 内容 |
| 検査方法 | 磁場と電波を利用して、膵臓や膵管の詳細な画像を撮影 |
| 目的 | 腫瘍の性質、膵管の狭窄や閉塞の評価、転移の有無の確認 |
| 特徴 | 軟部組織の描出に優れ、膵管や胆管の異常を詳しく観察可能 |
| デメリット | 撮影時間が長く、体内に金属がある場合は検査が受けられないことがある |
MRI検査は、CT検査では分かりにくい膵管の異常や腫瘍の詳細な性状を調べるのに有効です。
PET-CT検査
PET-CT検査は、がん細胞の代謝の活発さを画像化するPET(陽電子放射断層撮影)と、詳細な体内構造を撮影するCTを組み合わせた検査です。
膵臓がんの診断では、他の検査で確認しにくい転移の有無を評価するために用いられることがあります。
特に、小さな転移巣やリンパ節転移の検出に有効とされています。
| 項目 | 内容 |
| 検査方法 | 放射性薬剤(FDG)を静脈注射し、がん細胞の糖代謝の活発さを画像化 |
| 目的 | 転移や再発の有無の評価、他の画像診断ではわかりにくい病変の検出 |
| 特徴 | 体全体を撮影でき、微小な転移や隠れた病変を発見しやすい |
| デメリット | 膵臓がんはFDGの集積が弱いことがあり、診断精度が限定的 |
PET-CTは膵臓がんの初期診断よりも、転移や再発の評価に適しています。
CTやMRIと組み合わせて使用することでより正確な診断につながるため、総合的に評価します。
膵臓がんの血液検査(腫瘍マーカー)
膵臓がんの診断には画像検査が主に用いられますが、血液検査による腫瘍マーカーの測定も補助的な役割を果たします。
腫瘍マーカーとは、がん細胞や体の反応によって血液中に増加する特定の物質のことで、膵臓がんではCA19-9やCEAなどが重要視されます。
| 腫瘍マーカー | 特徴 |
| CA19-9 | 膵臓がんで高値を示すことが多いが、早期がんでは反応しにくい |
| CEA | 消化器系のがんで上昇することがあり、膵臓がんでも一定の割合で増加 |
| DUPAN-2 | 進行した膵臓がんで高値を示し、CA19-9と併用されることが多い |
| SPan-1 | 早期膵臓がんで上昇することがあり、診断補助として活用 |
血液検査は膵臓がんのスクリーニングや治療効果のモニタリングに役立ちますが、単独での診断精度は低いため、画像検査と組み合わせて総合的に評価します。
膵臓がんの内視鏡検査
膵臓がんの診断では、内視鏡を使用して膵管や胆管の状態を詳しく調べることができます。特に、がんが膵管を圧迫して狭窄や閉塞を引き起こしている場合、内視鏡検査が有効です。
| 検査名 | 特徴 |
| ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影) | 内視鏡を使って膵管や胆管に造影剤を注入し、X線で詳細に観察する。膵管の狭窄や閉塞を確認しながら、胆管ドレナージなどの処置も行える |
| EUS(超音波内視鏡) | 内視鏡の先端に超音波装置を搭載し、膵臓を高解像度で観察する。特に小さな腫瘍の検出に優れている。 |
膵臓がんの生検組織診断
膵臓がんの確定診断には、必要に応じて生検による組織診断が行われることもあります。
生検では、腫瘍の一部を採取し、顕微鏡で詳しく調べることで、膵臓がんの種類や悪性度を確認します。
| 生検方法 | 特徴 |
| EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引生検) | 超音波内視鏡を使い、胃や十二指腸の壁を通して腫瘍の組織を採取。膵臓の腫瘍を直接確認しながら安全に組織を採取できる。 |
| ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影) | 胆管や膵管に細い器具を挿入し、細胞を採取する |
| CTガイド下生検 | CT画像を見ながら、皮膚の上から針を刺して腫瘍の組織を採取 |
がん細胞の数が少ない場合や採取が困難なケースでは、繰り返し検査が必要になることもあります。
膵臓がんの新しい治療法:免疫療法
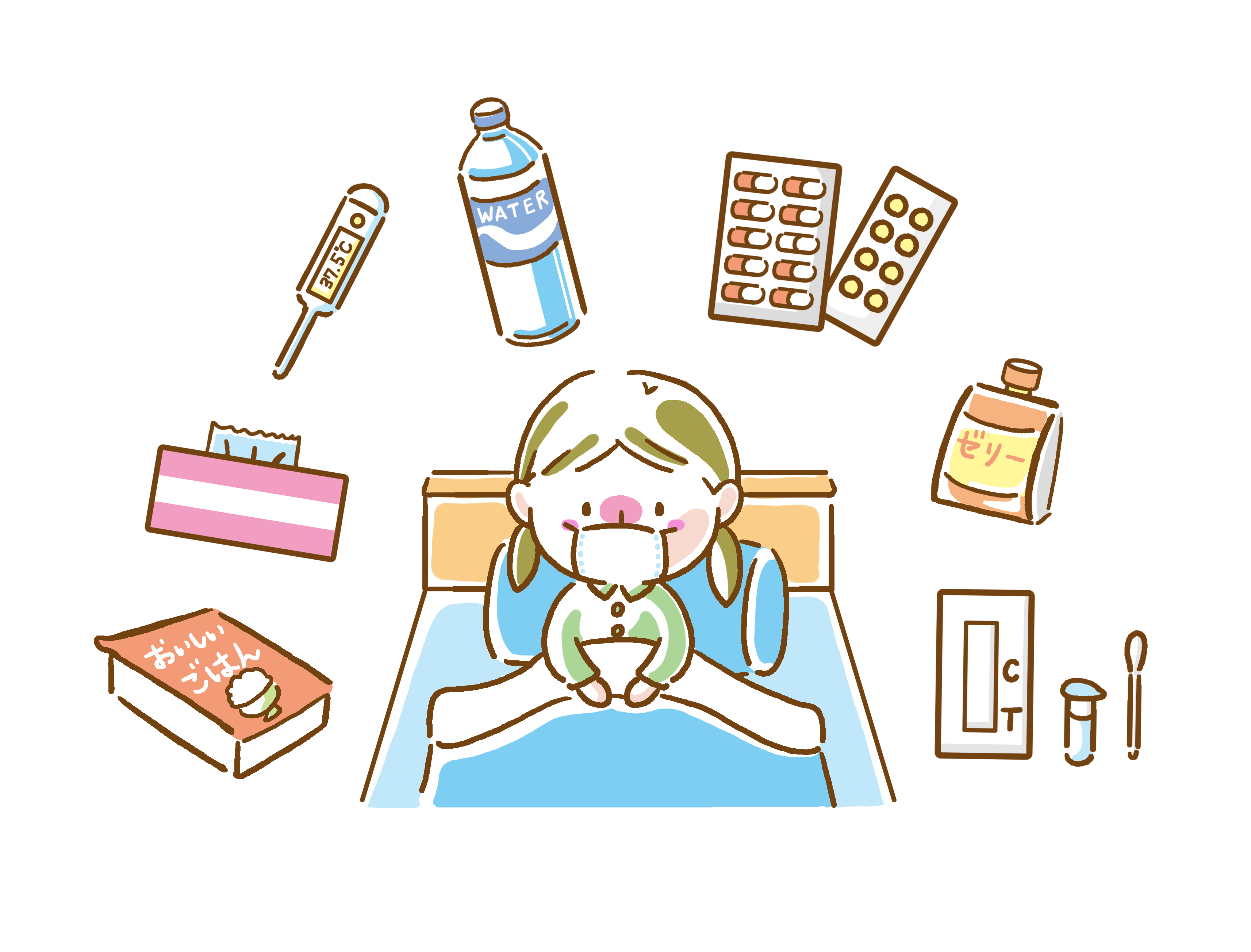
膵臓がんは、初期段階ではほとんど自覚症状が現れないため、発見時には病状が進行しているケースが少なくありません。
そうしたケースで、放射線治療や薬物療法に加え、近年注目されているのが免疫療法です。
免疫療法は近年研究が進み、より高い治療効果が目指されおり、その一つに6種複合免疫療法という治療があります。
6種複合免疫療法は、がん免疫療法の1つで、私たちの体の中にある免疫細胞を一度体外へ取り出し、活性化・増殖させて体内へ戻し、がんと闘う力を増強させる療法です。
以下、免疫療法の中で特に注目の6種複合免疫療法について詳しく解説します。
副作用が少ない6種複合免疫療法
「6種複合免疫療法」の特徴を3つ紹介します。
①副作用が少なく、体への負担が小さい治療法である
患者さまご自身の免疫細胞を使用するため、抗がん剤のような強い副作用がほとんどありません。
そのため、他のがん治療で治療継続は困難と判断された場合でも、6種複合免疫療法なら治療を継続できる可能性があります。
②がん3大療法との併用が可能で、ほぼ全てのがんに対応する
がん3大療法(外科手術/化学療法/放射線治療)との併用が可能で、一部(T細胞・NK細胞・NKT細胞型白血病/T細胞・NK細胞・NKT細胞型悪性リンパ腫)を除く、ほぼ全てのがんに対応します。
また、手術後に残ったがん細胞にも対応し、がん細胞増殖の抑制、再発・転移の予防にも効果的です。
③入院が必要ないため、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができる
6種複合免疫療法は、採血と点滴だけの通院治療です。
そのため、入院の必要がなく、患者さまの生活のリズムを変えることなく治療を行うことができます。
6種複合免疫療法の治療効果
以下は、6回(1クール)の治療を終えた患者さまの治療効果です。



A判定〜C判定の約79%の方は腫瘍の進行が抑制されたと評価し、さらにA判定〜B判定の約26%の方は腫瘍の減少が認められた状態となりました。
また、6種複合免疫療法の大きな特徴として、さまざまな部位のがんに対応できるという点があります。
以下、6種複合免疫療法で過去に治療したがんの一例です。ほぼ全てのがん種に対応しているため、以下に記載のないがん種や希少がんでも、治療可能です。

詳細は以下よりお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
専任のスタッフが丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
0120-271-580 受付時間平日9:00~18:00/土曜9:00~13:00